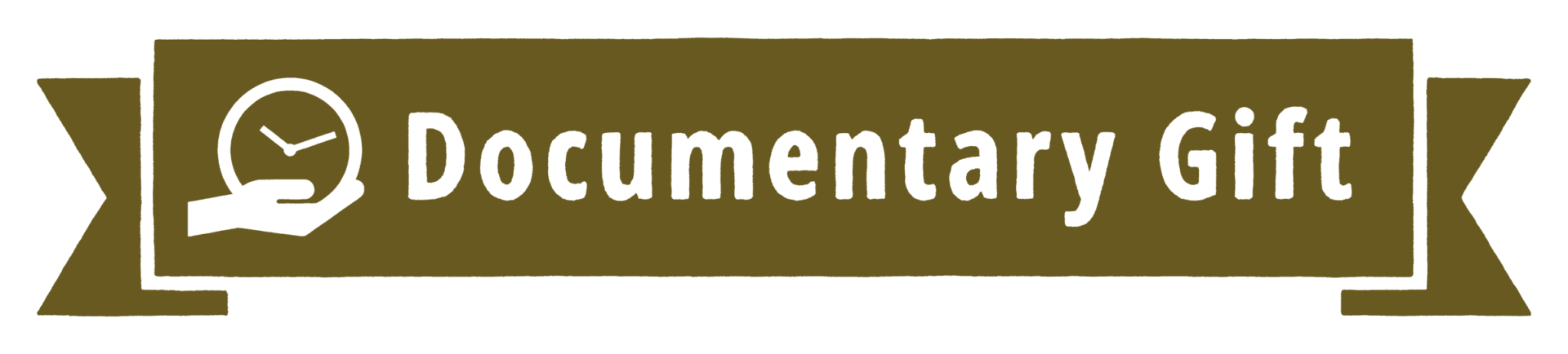「現実だった。
本当にいなくなっちゃったよ。」
わたしたちは、結婚して2年8ヶ月経つ夫婦。
いっしょに居るようになってから4年近くになる。
まだまだ短いこの間、楽しい日も、ケンカをしてもめた日も、いっしょにおいしい食事をする時間を通して、自分たちなりの夫婦の形をつくりながら暮らしてきた。
そんな中で、5月頃に夫の親しい友人が亡くなり、どちらかが向こう側に行ったときのことを想像した。
「ごはんを食べること」はとんでもなく日常だが、死ぬことも日常の中でこんな風に身近で起きる。
この先、歳をとったら、もっと普通に起きるものだと感じるようになるのだろうか。
世の中っていうのは、死というものを特別なものとして、そういうものを見ないように避けて通る。
でも、現実は親しい人の死も身近に感じながら生きていかなきゃいけない。
親が自分よりも先にいなくなるのは、孫の顔を見れずに亡くなるのは、事故などでとつぜんいなくなるのは、どうしたってつらい。
ただ、どれだけ現実逃避をしようとしても、日常の中にあるつらさは、日常の中でしか癒せないのだ。
わたしは、おいしい時間を味わうことで救われたあの日のことを記しておこうと、もう一度感情の動きの記憶を手繰り寄せながら、今言葉を綴っている。
「おいしい」は純粋なまま人の記憶に結びつく
買い物をしながら、「今日は何を食べようかな。明日の昼は何を食べようかな。妻のお弁当のおかずは何がいいかな。」
職業はミュージシャン。トランペットを吹いていて、フリーランスで仕事時間の調整をしやすいことから、日々の料理をしてくれていることが多い。
毎日の献立を考えるのは、なかなか大変なものだが、好みの味のごはんを二人で食べることを重視して自炊をする。
夫は、過去に外で食べたおいしかった味をより自分たちの好みに仕上げてつくってくれたり、一度つくったことのある料理も毎回さらにおいしくなるようにアレンジをしてくれる。
だから、わたしたちはいつも「前に食べたときもおいしかったけど....今日はもっとグレードアップしたねぇ。」と話す。
おいしかった時間はなぜこんなにも記憶に残るのだろう?
広島出身の友人が、少し前に料理人のお父さんを脳出血で亡くしたときのこと。
お父さんは、だし巻き卵名人だった。
地元のみなさんに何十年も愛される逸品になっていたそうで、来る日も来る日も卵に取り憑かれたように、だしまきを巻いて、病院で亡くなる前の最後まで「だしまき、だしまき、、」とつぶやいていたお父さん。
ひょうきん者で、お世話になった人だけでなく、普段あまり出向かない人にまで車でだしまきを配りに行っていたため、通夜、葬式、と驚くくらいの人が会いにきて、口々に「こないだ、だし巻き持って来てくれちゃったばっかりよ!」と言われたそうだ。
立派な偉業を残すことよりも、亡くなったときに「あの人のだしまきは美味しかったなぁ」「とってもゆかいで良い人だったなぁ」と憶えてくれている人がいる。
その記憶を周りの人が話してくれる人生は幸せだ。
「おいしい」が結びつける人のうれしい記憶は、こうやって純粋なまま生きつづけてくれるのだと思う。
いっしょに食べる人が、自分の「おいしい」をつくる
 わたしたち夫婦は、いつも食事のときには目の前の食事の話しかしないことが多い。
わたしたち夫婦は、いつも食事のときには目の前の食事の話しかしないことが多い。
ほかの話がまじることもあるが、たいがいは、いかに今食べている料理がおいしいかの話。
「この唐揚げは...絶品だよね。」
「さっきの煮付けはよかったなぁ。」
仲の良い友人でも、「あぁ、おいしかったね」と共感はできても、ぜったいに食事以外の話に夢中になるし、食事だけの話をするほうが、むしろむずかしい。
外食をしているときに、わたしは笑って「わたしたち食事の話以外してないね」と言うと、夫からは「ぜんぜん問題なくない?」と返ってきた。
二人とも、むしろおいしく食べている相手を見ること、おいしさをしっかり味わっている自分のほうが心地よい。
これは我が家に限る感覚なのだろうか...と思っていたところ、ほぼ日を経営されている糸井重里さんも同じことを言っているのを見つけた。
すごく仲のいい友だちと食事に行っても、その食事についてだけ話すっていうのは、まずできないんですよ。どれだけ仲がよくてもさ、その先に、「会話をする必要がないほどの関係」っていうところまでは、いかないじゃない。
(via ほぼ日刊イトイ新聞 「黄昏」)
この記事を読んで、夫婦とはこうゆうものなのかもしれないと感覚的にわかった気がした。
いつか、歳をとって、どちらかが先にいなくなってしまい、ぽっかり穴があいてしまうおじいちゃん、おばあちゃんの気持ち。
わたしたちは、お互いに「おいしい」と言いながら食べたほうが、おいしいのだということを知っている。
食事に集中できるのに一人じゃない。
この関係はいっしょに暮らす夫婦だからこそなのだろう。
ふと、どちらかが一人でこの「おいしい」を味わうことになった世界を一瞬想像して、せつなくなる。
同時に、そのときを迎えても、いつものこの時間がどれだけいい時間であったかと思い出してはあたたまる気持ちを残せるように、今のおいしさを噛み締めたいと思えた。
ただ「おいしい」を一緒に感じることが、その時間をうめる全てだった
夫の様子がいつもと違う感じに気づいたときのこと。
会話の反応が悪く、少しうわの空のようだった。
仕事でも譜面などの忘れ物が続いたりと、少し違和感を感じていたので、「何かあった?」「体調悪い?」と聞いていたら、体調は悪くないけれど、少し間をあけて、ちょっと理由があると言う。
そして、こう続けた。
「昔からの仲間が亡くなって。」
わたしは、自分にとって、いちばん身近だった死は、父方の祖父を家でおくったとき。
二世帯で、寝たきりのおじいちゃんのめんどうを海外駐在中の父に代わり母がみていたので、最期をむかえるときは病院ではなく実家だった。
学生で若かったわたしは、家で看取ったときに死んだ人を目の前にした初めてのこわさと「あぁ、隣に住んでいるのに、なんでもっと顔を見に来なかったのか」後悔した。
今まで息をしていた者が突然息をしなくなるという嘘のようなほんとうの出来事に出会ったとき、どんな人でも考えさせられる。
それまで結婚にまったく興味のなかった兄が、結婚をして家族、孫におくられる人生は幸せだと、これをきっかけに結婚観が変わったくらいだ。
夫が、仲間だと話すその人とわたしは会ったことはないのだが、現在40歳の夫と同年代で若い頃からの親しい仲。
以前に出したCDの録音にも参加してくれているピアニストだった。
ミュージシャンの言う「昔からの仲間」とは、売れる売れないに関係のない頃から、いっしょにやってきた同志の絆が強く、特にジャズミュージシャンはあまり言葉は交わさなくても音を合わせてみるだけで、「成長したなぁ」とか「今こんな風にやっていきたいのかな」とか、読み取れるような関係。
━━いつでも声をかければまたセッションができる。
そう思いながらの突然の知らせで、実感はまったくわいてこない。
お通夜へ行く前にずっとわたしに言っていた言葉は「納得できない」というものだった。
心筋梗塞や脳梗塞なのか、はっきりはわからない。
でも、人一倍太っていたとか、病気を患っていたわけではなく、最近まで周りの仲間はいっしょにライブをしていた。
同じ40歳で、ちゃんと健康診断に行かないとなぁなんて意識が強くなる年齢でもあって、これからじゃないか。
だから、納得できない。
納得なんてしたくない。
そのとき、わたしは何も言えなかった。
翌日、お通夜で、何とかちゃんと友人の顔をみて、現実に引き戻された夫から携帯に届いたメッセージを開ける。
「やっぱり、現実だった。本当にいなくなっちゃったよ。」
こんなときに、どんな言葉をかければいいのだろう?
経験値が豊富な親なら、どうするだろう?
どんな言葉も見つからず、精一杯の「家で待ってるから、いっしょに飲む?」という質問に、「飲みたい」と返ってきたので、ほっとした。
なんだか無性に、生を感じる必要がある気がして、ごはんとお酒のおいしさを身近な人と感じる、それだけの時間が必要な気がしたからだ。
広島出身の友人もお父さんのお葬式後、「安堵なのか、バカみたいに食べれた。こんな時でも、おいしい物をおいしいって感じて食べれる幸せを噛み締めた。」と言っていた。
そう話す彼女は妊娠中で、実はお父さんがいちばん孫を楽しみにしていた。
だからこそ、おなかの子との今を生きるために懸命に食べる——。
わたしは、お通夜のあった日、泣かずに帰ってきた夫といつものようにおいしくごはんをつまみながら、お酒を飲んだ。
━━その後に行った夫のジャズライブの日。
壁を見ると目に入ってきたのは、亡くなった夫の友人の名前が書いているフライヤー。
他のミュージシャンによる別日のライブと一緒に載っているものだったが、その友人のライブの日付は亡くなった後のものだ。
わたしは、二人で帰る電車の中で、iTunesから当時のCDに入っている曲を再生して、夫の作品に参加してくれたことに感謝をしながらピアノのソロに耳を傾けて帰った。
帰宅後は、やっぱり決まっていっしょにごはんを食べて、いっしょに眠る。
楽しいことを幸せだと思うことは誰にでもできるけれど、問題はつらいことをどう乗り越えていくかだろう。
この人となら幸せになれると思うことは簡単でも、もし二人で不幸せになったときもいっしょに踏ん張れると思えるか。
そう思える関係であるからこそ、何げない日常の中で「夫婦の食事をもっとおいしい時間にしたい」と真剣にむきあいつづけられるのかもしれない。
いつも心をうめてくれる、いつもの日常を過ごすほどに。
「これが食べたい」を見過ごさず、おいしい今日を増やすこと
仕事で疲れているときなんて、何が食べたいか頭がまわらず、つい、「パスタでいい」「和食でもいい」と言ってしまうと、よく夫から「パスタ『が』いい」に直されることがある。
めんどうだなぁ(笑)と思ったりするけれど、これは....正しい。
そのセリフをつづければつづけるほど、まぁいいかという思考はクセになる。
仕事や洋服なら好みをはっきり言えても、毎日のごはんはおざなりになりがちになる。
特に一人だとよけいに自分だけのごはんに手をかける気がおきない。
これでいいと思って食べるごはんは、こんなものだろうという味しかしないし、自分自身もその程度でしか味わえない。
でも、これがいいと思って選んで食べると、やっぱりおいしいと思える。
あのときのあの味が食べたい。
またあのお店に食べに行きたい。
あの人といっしょに。
「この人とこれが食べたくてね」という想いで身近な人と過ごす今日のおいしい時間は、必ずその後の人生を照らす記憶を残してくれるものだというのが今の自分にはわかる。
きっと、わたしはこれから何度も特別であり日常である自分たちの食事の時間に救われつづけるだろう。
選んだ食事を選んだ人と味わう、一人じゃない暮らしに。
だから、夫も友人のことを思い出してつらくなったときに、こんな風に記憶を重ねてくれていたらと思う。
━━つらかったあの日、家に帰って夫婦いっしょにおいしくごはんを食べてお酒を飲んだんだよなぁ。あいつ、あいかわらずのすごい食欲で笑ったんだ。
竹内 亜希子 Akiko Takeuchi
-植物療法士(フィトセラピスト)
-女性の健康経営推進員
-健康経営エキスパートアドバイザー
幼少より10年間シンガポールで暮らす。
帰国後、会社員として働く中で余白時間を奪われる社会の渦に揉まれ、20代半ばに坐骨神経痛を一年患い、根本改善のためにストレスケアにフォーカス。食生活改善と植物療法を実践し、3ヶ月で完治。
植物療法士として、働く世代の女性の心身のセルフケア、ストレスやホルモンバランスの体の変化をコントロールできる体質づくりを指導。
オリジナルハーブティーブレンド 販売、カフェ等の店舗向けオリジナルハーブティー商品企画・提供、大切な人とのヘルシーな時間を追求するカルチャーメディア『Documentary Gift 』を運営。
現在は、ヘルスケア企業にて、健康保険組合や企業に向けた生活習慣改善プログラムの提供・運営や健康経営推進、中でも女性の健康づくりに注力。
働く女性にとっての「からだにいい生き方」や予防のための「セルフケア」を継続する暮らしのつくり方を伝えている。
趣味:日々の楽しみは、心打つライブと毎日調合するハーブティー、そして家族と食卓を囲う時間。